
一般眼科

一般眼科
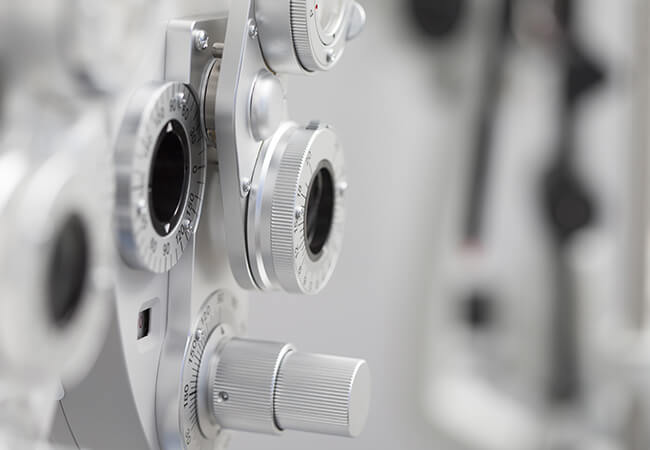
眼科は目と目の周囲に関する病気全般をみる診療科で、乳幼児から御高齢の方まで幅広く診療致します。人は外部からの情報の8割を目から得ているとされ、情報の視覚化が進む現代では“ものをしっかり見る”ことは日常生活において極めて重要です。
眼の症状は、充血、眼のかゆみ、まぶたの腫れなどの軽度なものから、緑内障や糖尿病網膜症、加齢黄斑変性症といった大きく視力に影響するものまで様々です。中には初期症状は軽度でも、進行することで生活に影響を及ぼす視力障害を残す病気も存在します。早期発見・早期治療によって進行を遅らせ失明を防ぐことが重要になりますので、眼の症状で心配なことがありましたら気軽に御相談下さい。
当院は、患者様の眼の健康を第一に考え、寄り添い、生涯にわたる皆様の視生活をサポートさせて頂きます。
このような症状の方はご相談下さい。
ドライアイの症状は、目の乾きだけでなく、かすみ、まぶしさ、疲れ、異物感、充血、涙が出るなど様々です。加齢による涙の量や質の低下、長時間の近見作業、生活環境(低湿度、エアコンの風が当たるなど)、コンタクトレンズ装用などが原因となりますが、中には膠原病などの全身疾患に合併することもあります。
治療は、涙の不足成分を補ったり、目の炎症を抑えたりする目薬や、涙点に栓(涙点プラグ)をして涙をためる治療などで改善を目指します。
目はカメラの様な構造をしています。角膜と水晶体といったレンズの役割をする組織が、後方にある光を感知する神経の膜(網膜)に焦点を合わせることでものが見えます。この焦点が網膜の前方にずれた目を近視眼といい、後方にずれた目を遠視眼と呼びます。
近視は遠くの像がぼけて見え、近くを見る時は眼鏡なしでもはっきり見ることができます(近視の程度による)。遺伝や目の成長、長時間の近見作業(読書、勉強、スマ-トフォン等)などが原因として挙げられます。遠視は遠近ともにピントが合いませんが、目の筋肉を使うことでそれを可能にしています。特に近見時に筋肉を使うので、加齢とともに近くが見にくく疲れやすくなります。近視同様、遺伝的な要因が関係していると考えられています。乱視の主な原因は角膜や水晶体の歪みです。焦点が1箇所に集まらなくなり、ものがぼけて見えます。
これらの屈折異常は一般的には眼鏡やコンタクトレンズで矯正します。
近年では、就寝時にハードコンタクトレンズを装用して日中は裸眼で過ごせるオルソケラトロジーの他、レーシックやICLといった屈折矯正手術もあります。
新聞やスマートフォンなど手元の文字が見にくい、ぼやけるといった症状が老視(老眼)です。40歳前後から自覚することが多く、眼の調節機能が低下して近くのものにピントが合わなくなります。老視は眼鏡やコンタクトレンズで矯正します。
若い方でも、スマートフォンやタブレットなどを長時間見続けることで、仮性近視という老視のような症状が起こることがあります。
眼を使う作業を続けることで、目の痛み、かすみ、充血などの症状や、頭痛、肩こり、吐き気などの全身症状が現れ、十分な休息や睡眠をとっても回復しない状態をいいます。緑内障や白内障、ドライアイなどの眼の病気が原因で眼精疲労が生じることもありますが、合わない眼鏡を使用したり、老視の初期などで無理な近見作業を長時間行った場合に生じます。最近では、パソコンやスマートフォンなどを使用する機会が増えているため眼精疲労を訴える患者様も増えています。
治療は、原因が特定できればその排除が必要です。眼鏡が合わない場合は作り直し、目の病気が発見されれば治療します。近見作業が多い場合は、適度な休息を挟み、目の筋肉の緊張を取るためにホットアイマスクなどで目を温めることも有用です。点眼薬や内服薬が有効なこともあります。
まぶたにある汗や脂の分泌腺や毛穴に細菌が感染し症状を引き起こします。まぶたの腫れ、赤み、痛みを伴い、腫れた部分が破れ膿(うみ)が出ることもありますが、出てしまえば症状は回復に向かいます。
治療は抗生剤の点眼や内服、軟膏を使用しますが、症状が悪化した場合は切開し膿を除去することもあります。日頃から汚れた手で目をこすったりしないよう注意することが大切です。
まぶたにはマイボーム腺という脂の分泌腺があります。マイボーム腺の出口が詰まり炎症を起こし、まぶたの腫れ、しこりができるものを霰粒腫といいます。霰粒腫は麦粒腫と違いあまり痛みはありませんが、炎症を起こすと痛みが出ます。
治療は麦粒腫と同様に抗生剤の点眼や内服、軟膏を使用します。治りにくい場合はステロイドの注射や手術でしこりを取り除くこともあります。最近は切らない霰粒腫の治療法としてIPL(Intense Pulse Light)という光治療(自費)も有効とされています。
花粉やハウスダストなど様々な原因で、結膜の炎症とかゆみ、目の異物感(ゴロゴロする)、目やに、涙が出るなどの症状が生じます。花粉などによる「季節性」のものとダニやハウスダストなどによる1年を通じて症状のある「通年性」のタイプに分類されます。
治療は抗アレルギー剤の点眼や軟膏を使用します。
白目の表面を覆っている結膜が、黒目(角膜)上に覆いかぶさる様に伸びてくる病気です。三角形が翼のような形であることから「翼状片(よくじょうへん)」と名付けられました。結膜下の組織が異常に増殖することで生じます。症状としては、目の異物感、血管が増えることで充血が目立ったりします。特に症状が気にならない程度であれば経過観察で大丈夫ですが、黒目の中心近くまで伸びてくると乱視が強くなり視力低下をきたすため手術が必要になります。手術は日帰りで行いますが、再発がよく起こるので注意が必要です。50歳以降の中高年の方に多くみられる疾患です。
虫や糸くずの様なものが浮遊して見える症状のことで、見え方は人によって様々です。治療を必要としない加齢性変化の場合がほとんどですが、網膜剥離や眼球内の炎症や出血など、早急に治療を要する疾患の場合もあります。見え方からは原因を特定することはできませんので、飛蚊症が生じたらまずは眼科での精査をお勧めします。
治療は原因にもよりますが、必要に応じて点眼やレーザー治療、手術を要することもあります。
裂孔原生網膜剥離、糖尿病網膜症、加齢黄斑変性症、網膜静脈閉塞症など
目の中にある水晶体といったレンズの役割を持つ組織が濁る病気です。加齢とともに進行することがほとんどですが、アトピー性皮膚炎や外傷に伴うもの、先天的なものもあります。水晶体が濁ると、かすみや複視(ものが二重に見える)、暗所(夜間など)での見づらさ、また、光が散乱するため、まぶしく見えるなどの症状が現れます。進行すると視力が低下し、眼鏡でも矯正ができなくなります。
治療は基本的には手術を要します。
日本では40歳以上の約5%、つまり20人に1人に発症するといわれています。見えない場所(暗点)や見える範囲(視野)が狭くなるという症状が最も一般的ですが、病気の進行は緩やかで、視野障害があっても初期の段階であれば自覚しないことがほとんどです。目の圧(眼圧)や血流障害による視神経の萎縮が発症に関わっていると考えられており、一度障害された視神経は回復しないため進行させないことが治療の目的になります。代表的な失明する疾患ですので40歳を過ぎたら眼科を受診して緑内障の有無を調べることを勧めます。
治療は眼圧を下げることが最も有効とされています。基本的には点眼での治療がメインとなりますが、点眼のみで不十分な場合や薬のアレルギーなどで点眼が使用できない場合は、レーザーや手術治療などが必要になることがあります。
TOP